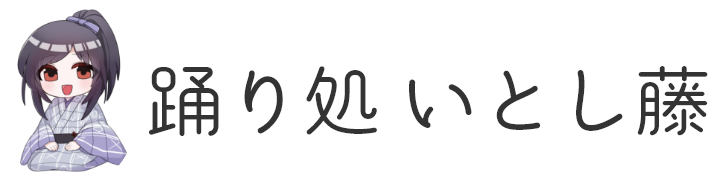各コースで出来る事
-
初級

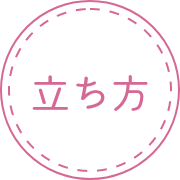





-
中級

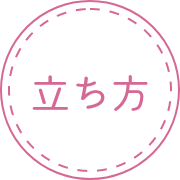





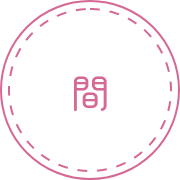

-
上級

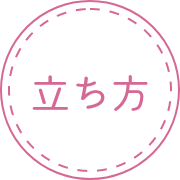





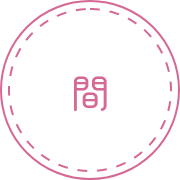



日本舞踊の歴史

日本舞踊とは伝統的な日本の踊りの相称になります。
700年代より「雅楽」、平安時代末期から鎌倉時代にかけて起こった「白拍子」、戦国武将の織田信長や豊臣秀吉が愛好家として有名な「能」。そして、1600年頃には「出雲の阿国」という女性により出来た「歌舞伎おどり」。また、江戸時代からは江戸の歌舞伎から生まれた『歌舞伎舞踊』があります。こちらと並んで、京都・大阪方面の『上方舞(地唄舞)』が発展し繋がっています。
以上のように様々な所から出来たものになります。しかし、盆踊りや阿波踊りなどの民俗舞踊は日本舞踊に含まれていないです。日本舞踊の簡単なイメージとしては「能」や「歌舞伎」の踊りの部分を抽出したような形が一番イメージしやすいかと思います。また演歌や歌謡曲などに振付をしたものを「新舞踊」と言いましてこちらは日本舞踊の1つとなっています。
流派について

流派とは、一言で申し上げると「技芸の継承システム」です。芸のスタイルを次の世代に崩れることなく継承するために正式な継承者として○○流△代目となり、所属するお弟子さんをまとめて○○流と言います。有名な流派として、五大流派(藤間流、西川流、花柳流、坂東流、若柳流)が御座います。伝統芸能として次の世代に継ぐことを大切にしてきたからこそ「流派」という家元制度が重用されてきたと考えられます。
しかし実のところ流派は数多く存在しており、「独自の形を生み出した・後継者問題・組織運営の不一致」など様々な理由が挙げられます。そのため元を辿ると五大流派から派生した流派と言う事も御座います。ゆえに流派の数は200を超えるとされています。